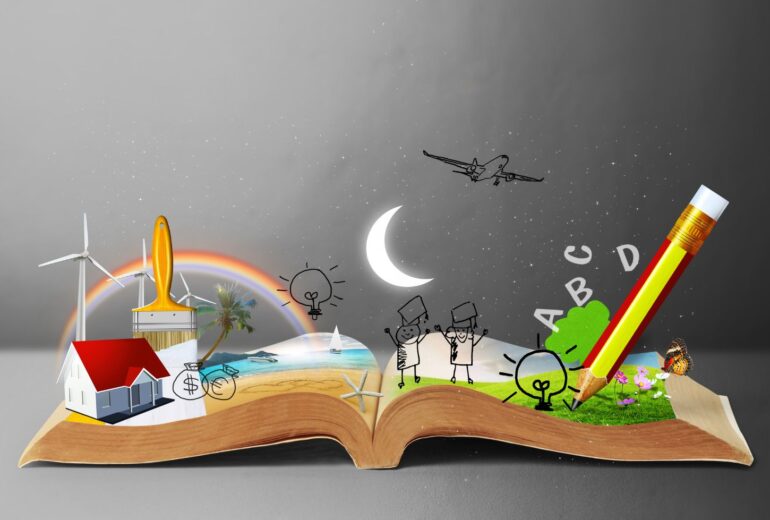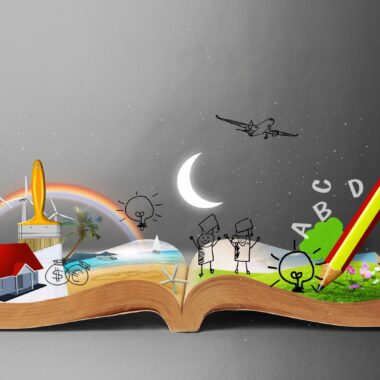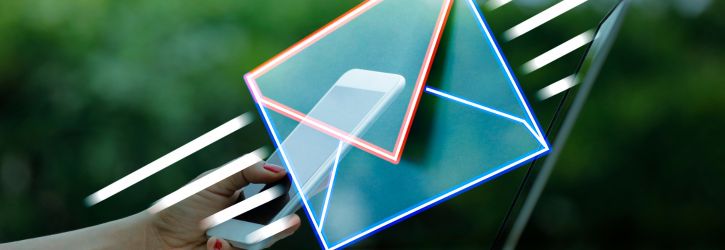はじめに
観光という言葉には、活性化、交流、経済効果といったプラスのイメージが根付いています。しかし今、「観光は本当に“いいこと”なのか?」という問題意識が、各地で聞かれるようになっています。
観光客が集中するあまりに、地域の暮らしが脅かされ、環境が損なわれ、地域の個性すら失われていく——それが「オーバーツーリズム」と呼ばれる現象です。
本稿では、こうした観光の「光と影」を改めて見つめ直し、次世代に向けた観光のあるべき姿を考えていきます。
オーバーツーリズムの構造と背景
世界観光機関(UN Tourism)は、オーバーツーリズムを「観光活動が地域社会や旅行者の体験に悪影響を及ぼす状態」と定義しています(*1)。これは単なる混雑ではなく、持続可能な観光の基盤を揺るがす構造的課題です。
この現象を引き起こす要因には、以下のような変化が複雑に絡み合っています:
- LCCの普及やビザ緩和による移動コストの低下
- 民泊や短期賃貸サービスによる宿泊手段の多様化
- SNSでの拡散による“映えスポット”への過度な集中
- ランキング文化やレビュー依存による観光の画一化
- 円安や訪日ブームによる外国人観光客の急増
旅行はもはや“非日常”ではなく、誰もが気軽に選択できる日常的なアクションへと変容しました。その結果、観光地側の受け入れ体制が追いつかず、多くの地域がキャパシティオーバーの状態に置かれています。
観光の光と影——地域が直面する多面的な課題
観光には確かに経済波及効果があります。しかし、同時に見過ごせない影響が各地で発生しています。環境破壊、地域生活の圧迫、文化の商業化など、観光の“影”の部分を丁寧に見ていきましょう。
環境への負荷
観光インフラの整備は、自然環境の改変と表裏一体です。森林伐採、水資源の枯渇、生態系への影響、さらにはCO₂排出の増大といった問題が深刻化しています。海外の例では、バリ島での水不足や、タイ・ピピ諸島でのサンゴ礁の白化が象徴的です。
地域住民の生活圧迫
通勤・通学の混雑、深夜の騒音、ゴミ問題、無断撮影や私有地への立ち入りなど、観光客による生活圏への侵食が進んでいます。住宅不足と家賃高騰により、地域住民が生活拠点を維持できない「観光地のジェントリフィケーション(*2)」も各地で問題化しています。
地域経済の偏りと文化の消耗
観光によって潤うのは一部の事業者に限られ、収益が地域に還元されにくい構造も課題です。地元商店街が土産物店一色になり、生活インフラとしての機能が失われるケースも見られます。さらに、祭りや伝統行事が“見せ物”化し、文化本来の意味が薄れていく危うさも指摘されています。
観光の再設計——分散と共創によるアプローチ
持続可能な観光を実現するには、“集中”から“分散”へ、“消費”から“共創”への転換が必要です。
時間・空間の分散化
- 京都・清水寺では、早朝開門を導入しピーク時間の混雑緩和を図る
- 函館では展望台の混雑状況をリアルタイム表示し、分散訪問を促進
- 富良野では、四季を通じた体験型プログラムにより夏季集中を是正
これらの施策は「観光体験の質を落とさずに、地域の負荷を下げる」ことを目指した試みです。
地域とつながる観光体験の拡充
- 屋久島では自然保護と教育を両立したエコツーリズムが展開
- 埼玉県飯能市では、廃校を活用した里山ステイが人気
- 福井県鯖江市では、越前漆器の工芸体験による関係人口の創出
観光客を「一時的な来訪者(交流人口)」ではなく、「地域との関係性を築く当事者(関係人口)」として迎え入れることで、持続可能な関係が生まれます。
Brightが考える“つながる観光”
Brightでは、観光を「つながりによって人の可能性を広げる機会」と捉えています。
たとえば、日本ならではの食体験ワークショップ(TOKYO CUTE BENTO)を通じて、他にはない想い出を共に創ったり、季節を感じる農作業体験(suolo e suono 四季農園)に参加し、地域住民と共に汗を流す。そうした経験は、単なる思い出を超えて、関係性のきっかけを育みます。現地で出会った人と、帰ってからもSNSやイベントを通じて交流が続くケースも少なくありません。
観光を「一回きりの消費」ではなく、「継続的な対話」と捉え直すこと。これが、Brightが考える“つながる観光”です。
▶ TOKYO CUTE BENTO
▶ suolo e suono 四季農園
おわりに
観光とは、本来、他者の暮らしに触れ、自分の価値観を問い直す機会であり、新たな視点を得るものといえます。だからこそ、これからの観光は、必然的に「地域の課題解決や可能性の拡張」と結びついていくはずです。
消費型から共創型へ。その転換に必要なのは、敬意、対話、そして持続性です。
Brightは、観光を起点に、人と人、地域と社会がゆるやかにつながり合う未来の実現に貢献してまいります。
*1 出典:UN Tourism「オーバーツーリズム(観光過剰)」に関する概要
https://unwto-ap.org/…/overtourism_Ex_Summary_low-2.pdf
*2 出典:ジェントリフィケーション研究の変化と地域的拡大
https://www.jstage.jst.go.jp/…/72_56/_pdf

名古屋大学大学院修了後、外資系電機メーカーでグローバル営業に従事し、アジア・アフリカでの日系企業の進出支援に従事。現在は合同会社エネスフィア代表および株式会社BrightのCSOとして、SDGsビジネスマスターや脱炭素アドバイザーなどの資格を活かし100社以上の中小企業支援に実績。さらに、BSIジャパン認定アソシエイト・コンサルタントおよびB Corp認証取得支援コンサルタントとしても活躍中。