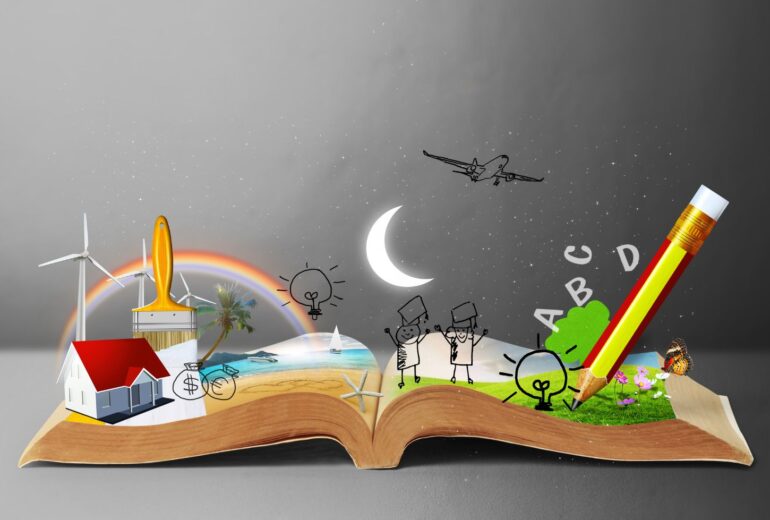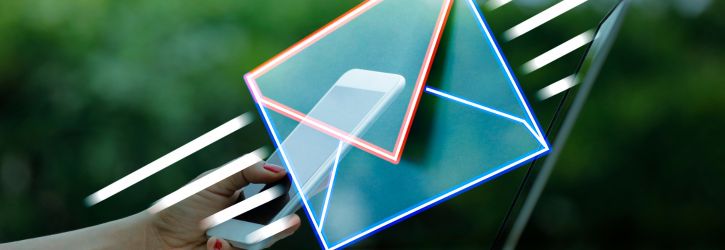規格外野菜とは何か
定義と背景
規格外野菜とは、農林水産省の「農産物規格」に適合しない野菜を指します。主にサイズや形状の不揃い、傷や虫食いが理由で市場流通から外されることが多いですが、その本質的な品質や栄養価には全く問題がありません。
しかし、規格外野菜の定義は単に「基準外」というだけでなく、より広い文脈で考えるべきものです。そもそも、日本の農産物規格は、流通の効率化や消費者の購買意欲を高める目的で設定されてきました。一方で、こうした規格は「見た目の美しさ」を優先するあまり、大量の食材が適切に活用されないまま廃棄されるというジレンマを生んでいます。
規格外野菜の現状と課題
驚くべき廃棄量
農林水産省によると、日本では年間約200万トンの規格外野菜が廃棄されており、これは全収穫量の約6%に相当します(東京ドーム約160杯分)。なお、世界における食料支援量(2021年)は約440万トンと言われているので、驚くことに、この約半分が規格外野菜として日本で廃棄されていることになります。また、単なる食品ロス問題にとどまらず、環境負荷の観点からも深刻な問題です。食品の廃棄は、廃棄処理に伴うCO2排出や水資源の浪費を招き、農業の持続可能性にも影響を与えます。
さらに、規格外野菜の廃棄は、食品ロス全体の一部を占めるだけでなく、サプライチェーン全体に影響を及ぼします。例えば、生産者は市場に流通できない野菜の損失を補うために、より多くの作物を生産せざるを得ません。これにより、農業における過剰生産が助長され、水や肥料の無駄遣い、ひいては農業従事者の負担増加にもつながります。
また、食品ロスは消費者レベルでも発生しています。規格外野菜が市場に出回る機会が限られることで、消費者は「形の整った野菜こそが良いもの」という固定観念を持ち続け、それがさらなる食品ロスの増加を招いています。この悪循環を断ち切るためには、消費者の意識改革とともに、規格外野菜を適切に活用するためのシステムが求められます。
規格外野菜が持つ本当の価値
規格外野菜の活用は、単なる食品ロス削減にとどまらず、多くの可能性を秘めています。
- 生産者の経済的安定:規格外野菜が市場で適正価格で販売されることで、生産者の収入安定につながります。
- 消費者にとっての価格メリット:見た目が異なるだけで、通常より安価に購入できるため、消費者にとってもメリットがあります。
- 環境負荷の軽減:食品の無駄を減らすことは、廃棄物処理の負担軽減や農業資源の有効活用にも寄与します。
- 地域コミュニティの活性化:規格外野菜の販売を通じて、地域の直売所やマルシェなどの活性化にもつながります。
規格外野菜を活用する取り組み
直売所やスーパーでの販売
道の駅や直売所では、規格外野菜が安価で販売されており、消費者は新鮮でお得な野菜を手に入れることができます。一部のスーパーでも、規格外野菜専用コーナーを設ける動きが広がっています。
オンラインプラットフォームの活用
「KURADASHI」や「食べチョク」などのオンラインプラットフォームが、規格外野菜の販売や無料配布を行っています。これにより、規格外野菜を手軽に購入する機会が増えています。
飲食業界での活用
最近では、飲食店や食品メーカーも規格外野菜を積極的に活用する動きを見せています。例えば、弊社運営のレストラン「ウマミタクラミ」では、規格外のフルーツや野菜を活用したランチメニューを提供し、持続可能な食文化の発展を目指しています。
私たちができること
日常の消費行動を変える
私たちは、規格外野菜を積極的に選ぶことで、食品ロス削減や農業の持続可能性に貢献できます。「見た目よりも本質」を大切にし、規格外野菜を選択する意識が重要です。具体的なアクションとして以下のことが考えられます。
- 規格外野菜を取り扱う店舗を利用する
- 道の駅や直売所、スーパーの規格外野菜コーナーを意識的に利用する。
- オンラインマーケットプレイスを活用し、自宅でも手軽に購入する。
- 農家直送の宅配サービスを利用し、規格外野菜の定期購入を検討する。
- 規格外野菜を使った料理の工夫
- カレーやスープ、スムージーなど、形が気にならない料理で積極的に活用する。
- 乾燥野菜やピクルスに加工し、保存食品として活用する。
- 形が不揃いな野菜を活用したレシピを家族や友人と共有し、食の楽しみ方を広げる。
- 規格外野菜の価値を周囲に伝える
- 家族や友人と情報を共有し、規格外野菜の購入を促す。
- SNSで規格外野菜を使った料理を紹介し、意識改革の輪を広げる。
- 規格外野菜をテーマにした食育イベントに参加し、子どもたちにも食品ロス削減の重要性を伝える。
- 食品ロス削減を支援する企業や団体を応援する
- 規格外野菜を活用した飲食店を利用する。
- フードバンクやフードシェアリング活動に参加し、食品ロス削減の取り組みに貢献する。
- クラウドファンディングを通じて、規格外野菜の活用を推進するプロジェクトを支援する。
- ライフスタイルの一部として取り入れる
- 毎月一度は「規格外野菜デー」を設け、意識的に規格外野菜を取り入れた食事を作る。
- 買い物の際に、見た目だけでなく、野菜の生産背景や農家の努力を意識する。
- 「もったいない精神」を意識し、家庭での食品ロスを減らす取り組みを実践する。
- 規格外野菜を取り扱う店舗を利用する
このように、私たち一人ひとりの小さな選択が積み重なることで、規格外野菜の活用が進み、持続可能な食文化が広がります。
コミュニティでの活動
地元の直売所や農家とつながり、規格外野菜を使った料理イベントを開催するなど、地域コミュニティを活用した取り組みも可能です。個人だけでなく、地域全体で食品ロス削減に取り組むことで、より大きなインパクトを生み出すことができます。具体的な活動例として以下のような取り組みが考えられます。
- 規格外野菜を活用した料理イベントの開催
- 地域の飲食店やコミュニティスペースを活用し、規格外野菜を使った料理教室や試食会を実施。
- 地元農家やシェフを招き、規格外野菜の魅力や調理方法を学ぶ機会を提供。
- フードシェアリングや交換イベントの実施
- 地域の直売所やマルシェで、規格外野菜を活用した食材交換イベントを開催。
- 余剰食材を地域内でシェアし、食品ロスを減らす仕組みを構築。
- 学校や教育機関での食育活動
- 小中学校や保育園で規格外野菜を使った給食や食育プログラムを実施。
- 規格外野菜の活用を通じて、子どもたちに「食の大切さ」や「もったいない精神」を伝える。
- 地域の企業や自治体との連携
- 地元スーパーや食品メーカーと協力し、規格外野菜を活用した商品開発を推進。
- 自治体の食品ロス削減施策に参加し、規格外野菜の認知度向上を図る。
- SNSやメディアを活用した啓発活動
- コミュニティ内での規格外野菜活用事例をSNSで発信し、賛同者を増やす。
- ブログやニュースレターを通じて、食品ロス削減の重要性を広める。
このように、個人の取り組みだけでなく、地域社会全体で規格外野菜の活用を推進することで、より持続可能な食文化を築くことができます。
「ローカル×グローバル」で食の未来を考える
規格外野菜の活用は、単なる食品ロス削減の一手段ではなく、持続可能な社会をつくる大きな鍵となります。地域の農業や食文化を見直し、私たち自身がより良い選択をすることで、より豊かな社会を築くことができるのです。
規格外野菜の問題だけでなく、「ローカル×グローバル」の視点でどのように社会を変えていけるのか、弊社株式会社Brightとして考えていることを、こちらの記事でまとめております。ぜひチェックしてみてください。
ローカル×グローバルの新時代~「コミュニティを生かしたライフワーク創造」への挑戦~
今こそ身に付けたいサステナビリティ・リテラシーとは?未来を見据えたキャリアの基盤作り
株式会社Bright広報部として、私たちは地域活性やSDGsをテーマに、持続可能な社会の実現を目指したブログを執筆しています。飲食や農業などの分野での実践や、現場経験を活かし、企業や地域の取り組みをわかりやすく発信。