1. はじめに
食品ロスという言葉を聞いたことがある方は多いでしょう。SDGs(持続可能な開発目標)が注目される中、食品ロス削減は持続可能な社会を実現するための重要な取り組みの一つとして位置づけられています。しかし、私たちの暮らしの中で、まだ食べられる食材が大量に捨てられている現状があるのです。
たとえば、日本では年間523万トンもの食品が廃棄されています(*1)。これを一人あたりの量に換算すると、年間約42kg、毎日おにぎり1個分(約114グラム)を捨てていることになります。これは驚くべき数字ですが、食品ロスの現状や背景を理解しなければ、実感が湧きにくいかもしれません。
本記事では、食品ロスの現状とその課題、そして具体的な削減策について深掘りし、私たちが今日からできる5つのステップを紹介します。食品ロス問題を解決するために、企業や自治体、私たち一人ひとりがどう関わり、どんな行動を取れるのかを一緒に考えていきましょう。
2. 食品ロスの現状
食品ロスとは、本来食べられるはずの食品が廃棄されることを指します。世界では年間約13億トンもの食品が捨てられており、これは世界の食料生産量の3分の1に相当します(*2)。特に日本では、輸入食材が多いために国内で廃棄される量が特に目立ちます。
事業系食品ロスと家庭系食品ロスに分けて考えると、2021年度時点で事業系食品ロスが279万トン、家庭系食品ロスが244万トンとなっています(*1)。事業系食品ロスの中では、食品製造業からの廃棄が最も多く、その次に飲食店、小売業が続きます。製造工程でのロスや、販売期限切れの商品、顧客の食べ残しなど、さまざまな原因が絡み合っています。
一方、家庭系食品ロスは「食べ残し」や「直接廃棄(使いきれなかった食材の廃棄)」が主な原因です。消費者が食品を無駄にしがちな背景には、賞味期限と消費期限の違いを理解していないことや、買い過ぎや調理過多といった食生活の問題が存在します。
食品ロスが社会に与える影響は甚大です。まず、廃棄物として処理する際に膨大なエネルギーが使われ、その過程で二酸化炭素(CO2)が排出されます。国連環境計画(UNEP)によれば、世界の温室効果ガス排出量の8〜10%が食品ロスに関連しているといいます(*3)。つまり、食品ロスを削減することは、気候変動を食い止めるための有効な手段でもあるのです。
加えて、食品を捨てるという行為そのものが経済的損失を生んでいます。廃棄物処理費用は自治体や企業の負担となり、結果として消費者にも跳ね返ってきます。さらに、飢餓や貧困が問題となっている世界の一方で、大量の食料が廃棄されているという現実は、倫理的にも見過ごせない問題です。
3. 日本の食品ロス削減策
日本では、食品ロス削減推進法(2019年施行)が中心となり、法整備と自治体・企業・消費者の連携による多角的な取り組みが進められています。特に、2030年までに2000年度比で食品ロスを半減させるという目標が掲げられており、政府や自治体、企業が積極的に取り組んでいます。
自治体の取り組みとして注目されるのが「長野県松本市の30・10運動」です。宴会時に乾杯後30分と終了前10分は席を離れず、料理をしっかり味わうというルールで、食べ残し削減を目指しています。また、京都市では販売期限を賞味期限まで延ばす取り組みを行い、廃棄量の大幅削減を実現しました。
企業の取り組みとしては、納品期限を緩和し「3分の1ルール」を撤廃する動きがあり、規格外品を積極的に販売することで流通段階でのロス削減を図っています。また、フードシェアリングサービスの「TABETE」など、売れ残り食品をアプリで割引販売する取り組みも普及しています。
さらに、消費者向けの啓発活動として「てまえどり」運動が注目されています。これは、スーパーの陳列棚で手前から商品を取ることで、販売期限の迫った商品の廃棄を減らそうという運動です。また、災害時の備蓄食品を日常的に入れ替える「ローリングストック」も有効な手段です。
4. 誰でもできる「食品ロス削減5ステップ」
食品ロスの削減は私たち一人ひとりの行動から始められます。ここでは、規格外品の活用やフードシェアの利用、家庭での食品管理、地域連携、保存方法の見直しといった「誰でもできる5つのステップ」を通じて、すぐに実践可能な食品ロス対策を具体的に解説します。
①食材の保存方法を見直す
食材が無駄になる主な原因は「保存ミス」。家庭内ロス(約247万トン/年)の約4割がここに起因。
取り組める内容
野菜は「呼吸する」ため、野菜室の詰めすぎを避ける(目安:7割収納)
「冷蔵保存」よりも冷凍保存で延命(例:余ったご飯、肉、きのこ、カット野菜)
脱気パック・コンテナ管理でニオイや劣化を防止
保存方法を学べるサイト:農林水産省「食品ロス削減ハンドブック」
大切なポイント
一部の野菜(じゃがいも・玉ねぎ)は冷蔵庫に不向き。光や湿気を避けて保存を。
一度冷凍→解凍した食材の再冷凍はNG。小分けが基本。
②職場や家庭で食品管理を徹底する
冷蔵庫やパントリー内の食材を把握し、「うっかり期限切れ」や「重複購入」を防ぐことでロスを削減します。
取り組める内容
買い物前に冷蔵庫内を写真撮影 or チェックリスト化
「賞味期限To Doリスト」を作成し、期限の近い食品から優先調理
職場では共用冷蔵庫やお土産コーナーの管理ルールを共有
大切なポイント
家族・同居人との共有がカギ。LINEグループやホワイトボードで可視化すると効果的
「常温品のストック期限」は忘れがちなので乾物やレトルトも定期確認
③規格外品の活用をもっと広げる
流通に乗らず廃棄されやすい規格外農産物や加工品の需要を増やすことで、生産現場の食品ロスを減らします。
取り組める内容
地元の直売所・道の駅・オンラインマルシェ(例:食べチョク「訳ありセット」)で規格外品を選んで購入する。
「もったいない食材特集」をしているスーパーや百貨店で応援購入。
大切なポイント
規格外品は「見た目」だけの問題で、品質・安全性には問題ないケースがほとんどです。
一方で鮮度が落ちやすいものもあるため、早めの調理が前提です。
④フードシェアリングサービスを積極利用する
飲食店・食品工場・小売店などで出る販売期限間近の食品を、捨てずに活用するルートを支援します。
取り組める内容
フードシェアリングサービスに関するスマホアプリ(例:TABETE、Reduce GO)をダウンロード
通勤や通学のルート上でテイクアウトできる食品ロス商品を購入する
企業や自治体の「もったいないプロジェクト」に登録し、SNS等で情報をシェアする
大切なポイント
商品は当日中に消費が基本(受け取り時間や保存方法に注意)
利用可能エリアが限られる場合があるので、都市部以外では地域の「食支援団体」も要チェック
⑤地域資源を活用したビジネスモデルを創る
余剰食材や地域の資源(農家・給食・飲食店など)を活用し、小さな循環モデルを育てることで社会的インパクトを創出。
取り組める内容
地元のフードバンク、子ども食堂、リユース食堂に未使用食品を寄付
コミュニティカフェで規格外野菜を活用した日替わりメニューを提案
農家と連携して「規格外野菜の週末マルシェ」をボランティアで支援
大切なポイント
食品衛生法により寄付できる食品の条件(未開封・賞味期限内など)を事前に確認
取り組みをSNSで発信することで仲間が集まりやすくなります
5. Brightが目指す「循環型社会」と食品ロス削減
Brightでは、コミュニティを軸とした活動により、食品ロスの削減に取り組んでいます。地域資源の活用やコミュニティとの連携を重視し、実際の店舗運営やイベント、企業支援を通じて、持続可能な取り組みを一歩ずつ形にしています。
食品ロスを抑える店舗運営とメニュー開発
Brightが運営する飲食店では、事前予約制を採用し、来店数に合わせた仕入れを行うことで、食材の過剰在庫を防いでいます。また、通常は捨てられる野菜の皮や芯などを、ドレッシングやピューレとしてメニューに活用する工夫も行っています。
さらに、地域の学生と連携し、規格外野菜を使ったレシピを一緒に考案する取り組みも行っています。これにより、学生にとっても食品ロスの現場を学ぶ機会となっています。
地域コミュニティとの共創イベント
TBSが主催するSDGsイベントでは、規格外の果物や野菜を使用したメニューを提供し、来場者に対して食品ロスの現実を伝える機会としています。
また、今後はBrightにて農業体験イベントを開催し、農業に触れることがあまりない方へ実際に農作業に参加できる機会を提供していく予定です。これにより、消費者が生産現場のリアルな課題に触れ、収穫物の規格外や未利用部分の存在に気づくきっかけを創出します。
社会戦略支援を通じた仕組み化
Brightは、自社の取り組みにとどまらず、他の中小企業に向けた支援も行っています。具体的には、企業のブランディングや事業戦略に食品ロス削減を含む多様な視点を組み込み、実行可能な形で支援する取り組みです。
こうした支援を通じて、地域内外で持続可能な仕組みを広げていくことを目指しています。
6. まとめ
食品ロスは、私たちの身近な選択一つで大きく変えられます。「もったいない」を「価値」に変える視点を持ち、企業や地域と共に循環型の社会を創ることが求められています。今日からできる小さな一歩を、一緒に踏み出しませんか?
*1 環境省「我が国の食品ロスの発生量の推計値(令和3年度)の公表について」https://www.env.go.jp/press/press_01689.html
*2 FAO(国連食糧農業機関)「Global Food Losses and Food Waste – Extent, Causes and Prevention (2011)」https://openknowledge.fao.org/items/4a463cff-586d-433f-9124-af4b99246f91
*3 UNEP(国連環境計画)「Food Waste Index Report 2024」
https://www.unep.org/resources/publication/food-waste-index-report-2024
名古屋大学大学院修了後、外資系電機メーカーでグローバル営業に従事し、アジア・アフリカでの日系企業の進出支援に従事。現在は合同会社エネスフィア代表および株式会社BrightのCSOとして、SDGsビジネスマスターや脱炭素アドバイザーなどの資格を活かし100社以上の中小企業支援に実績。さらに、BSIジャパン認定アソシエイト・コンサルタントおよびB Corp認証取得支援コンサルタントとしても活躍中。

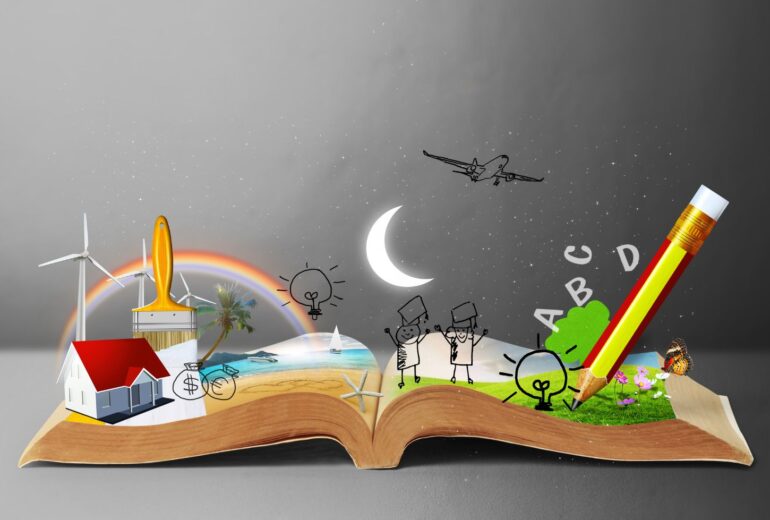







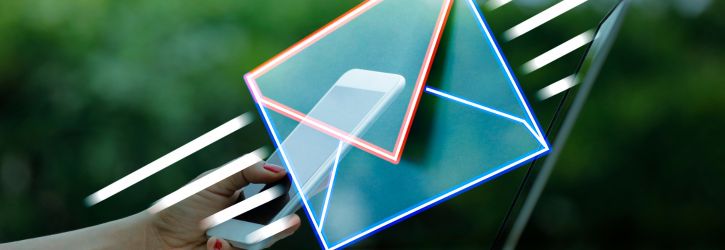

コメント