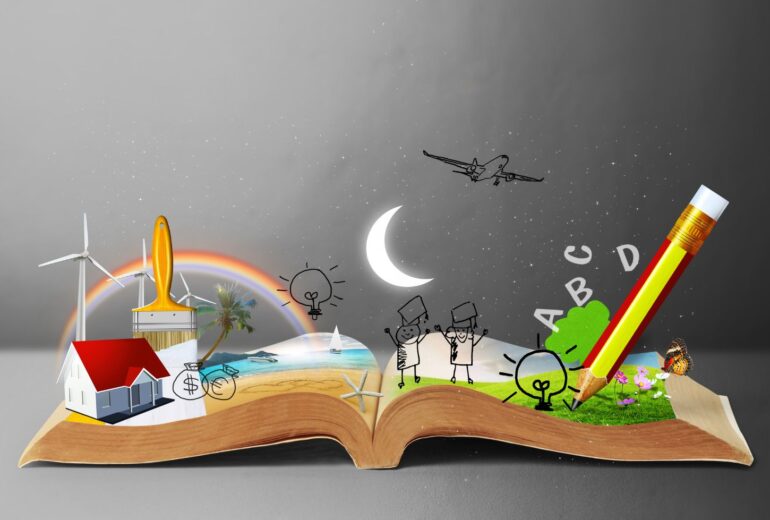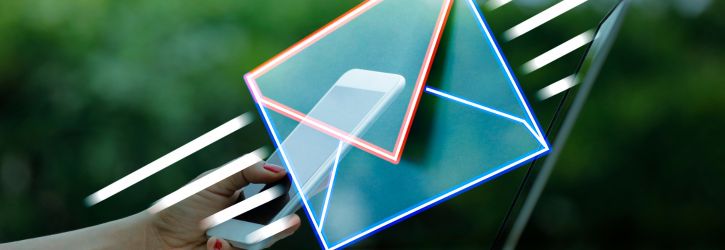はじめに
前回の記事では、近江商人の哲学である「三方よし」を発展させた「六方よし」についてご紹介しました。
この新しい考え方は、企業活動が経済的利益を超え、社会全体への貢献をどのように実現するかを示しています。この記事では、「六方よし」のうち、「作り手」「地球」「未来」に焦点を当て、サステナビリティの最新トレンドを掘り下げます。
作り手よし ~生産者とサプライチェーンに目を向ける~
「作り手よし」は、企業活動におけるサプライチェーン全体を視野に入れ、生産者や流通過程に携わる人々の働きやすさや満足度を向上させる視点です。近年、労働環境や人権問題が世界的な課題として注目される中、サプライチェーンの透明性確保が重要となっています。
企業の利益は、生産者や物流に関わる多くの人々の支えによって生まれています。彼らが健全で持続可能な条件で働ける環境を整えることは、企業としての責任であり、サステナブルな社会の構築に欠かせません。
作り手視点でのSDGsトレンド
- サプライチェーンの透明性向上:劣悪な労働環境や児童労働などの問題を解消するため、多国籍企業を中心にサプライチェーン全体の情報を公開する動きが活発化しています。
- 地産地消とローカルプロダクトの価値向上:地元の生産者を支援し、地域経済を活性化させる取り組みが注目されています。これにより、輸送コストや環境負荷を削減する効果も得られます。
- 倫理的サプライチェーン管理:ESGの一環として、環境配慮型の資材調達や労働環境改善が求められています。企業は倫理的なサプライチェーン運営を行うことで、ブランド価値を高めています。
作り手よしを実現する取り組み事例
- アパレル業界での透明性向上:多くのファッションブランドが、生産地や労働条件の開示を進めています。たとえば、「トレーサビリティ」技術を活用し、消費者が商品を購入する際に、その製造過程を追跡できるようにする取り組みが進行中です。
- 食品業界での地産地消プロジェクト:地元農家を支援し、新鮮な地元産食材を直接消費者に届けるプラットフォームが注目されています。これにより、生産者の収益安定化と輸送コスト削減を同時に実現しています。
- テクノロジー活用による労働環境改善:IoTやAIを活用して、生産現場の効率化や働く人々の負担軽減を図る動きがあります。これにより、労働時間短縮や安全性向上が実現されています。
作り手が健全な環境で働けることは、企業が提供する製品やサービスの信頼性を支える重要な要素です。また、働きやすい環境を提供することで、サプライチェーン全体のパフォーマンス向上と、社会的課題の解決を同時に達成することが可能になります。
目標8「働きがいも経済成長も」や目標12「つくる責任、つかう責任」の達成に向け、作り手よしを実践する企業が増えることで、持続可能な未来が広がるでしょう。
地球よし ~環境保全と再生可能な未来~
「地球よし」は、環境負荷を削減し、自然と共生する持続可能な社会を目指す視点です。気候変動、生物多様性の喪失、資源の枯渇など、地球規模の課題が顕在化する今、企業や個人に環境配慮型の選択が求められています。
地球視点でのSDGsトレンド
- カーボンニュートラルへの移行:2050年までにカーボンニュートラルを目指す目標は多くの国や企業が掲げており、再生可能エネルギーの導入やサプライチェーン全体の脱炭素化が進んでいます。
- 循環型経済(サーキュラーエコノミー):資源のリユース・リサイクルを徹底し、廃棄物を最小限に抑えるビジネスモデルが注目されています。製品の設計段階から、長寿命化や修理可能性を重視する取り組みも進んでいます。
- ネイチャーポジティブ:生物多様性への影響を最小限に抑え、森林保護や海洋保全などに積極的に取り組む企業が増えています。
地球よしを実現する取り組み事例
- 再生可能エネルギーの導入:大手IT企業では、自社のデータセンターを100%再生可能エネルギーで稼働させる目標を達成しており、カーボンフットプリント削減に寄与しています。
- サーキュラーエコノミーの実践:家電メーカーでは、製品のリサイクル材利用率を50%以上に引き上げる計画を実施し、廃棄物の大幅削減に成功しています。
- 森林再生プロジェクト:ある飲料メーカーは、製品の生産過程で使用した水を森林再生プロジェクトを通じて自然に還元する取り組みを行い、地域の生態系保護に貢献しています。
環境を守ることは、企業の持続可能性を高めるだけでなく、社会全体の幸福にも直結します。特に、目標13「気候変動に具体的な対策を」や目標14「海の豊かさを守ろう」、目標15「陸の豊かさも守ろう」を実現するために、「地球よし」を実践する取り組みが、企業と個人の双方にとって欠かせないものとなっています。
未来よし ~次世代への責任~
「未来よし」は、次世代が安心して暮らせる社会基盤を築くことを意味します。今の私たちの選択が未来の社会や環境に与える影響を考え、長期的な視点で行動することが必要です。
未来視点でのSDGsトレンド
- 持続可能な教育の普及:SDGs教育プログラムやリスキリング(再教育)の普及が進み、社会課題を解決する力を育む取り組みが注目されています。
- 未来志向のインフラ整備:クリーンエネルギー、スマートシティ、カーボンゼロビルディングなど、未来を見据えたインフラプロジェクトが注目されています。
- テクノロジーと社会課題の統合:IoTやAIなどの技術を活用して、交通、医療、教育などの社会課題を解決する取り組みが加速しています。
- 次世代のエンパワーメント:若者がリーダーシップを発揮し、社会を変革するための支援プログラムが増加しています。
未来よしを実現する取り組み事例
- SDGs教育の推進:ある自治体では、小中学校の教育カリキュラムにSDGsを取り入れ、地域課題の解決を通じて生徒が主体的に行動する力を育んでいます。
- カーボンゼロシティ構想:欧州の一部の都市では、2050年までにカーボンニュートラルを達成するため、交通インフラの電動化や建築物のエネルギー効率改善を進めています。
- スタートアップ支援プログラム:SDGsに基づいた新規事業の立ち上げを支援するため、官民連携によるファンド設立やアクセラレーションプログラムが各国で実施されています。
未来に目を向けることは、目標4「質の高い教育をみんなに」や目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」を達成するための鍵となります。「未来よし」を実践することは、次世代への責任を果たしながら、より良い社会を築く基盤をつくることにつながります。
まとめ:六方よしで描く未来への第一歩
「六方よし」の視点を取り入れることで、ビジネスは個人の幸福から地球規模の課題解決まで、幅広い価値を創造できます。売り手・買い手・世間・作り手・地球・未来というそれぞれの視点で注目されているトレンドを理解し、自分自身の新たなアンテナを立ててみましょう。
それが、あなたのキャリアやライフスタイルに持続可能な変化をもたらすきっかけとなるはずです!
名古屋大学大学院修了後、外資系電機メーカーでグローバル営業に従事し、アジア・アフリカでの日系企業の進出支援に従事。現在は合同会社エネスフィア代表および株式会社BrightのCSOとして、SDGsビジネスマスターや脱炭素アドバイザーなどの資格を活かし100社以上の中小企業支援に実績。さらに、BSIジャパン認定アソシエイト・コンサルタントおよびB Corp認証取得支援コンサルタントとしても活躍中。