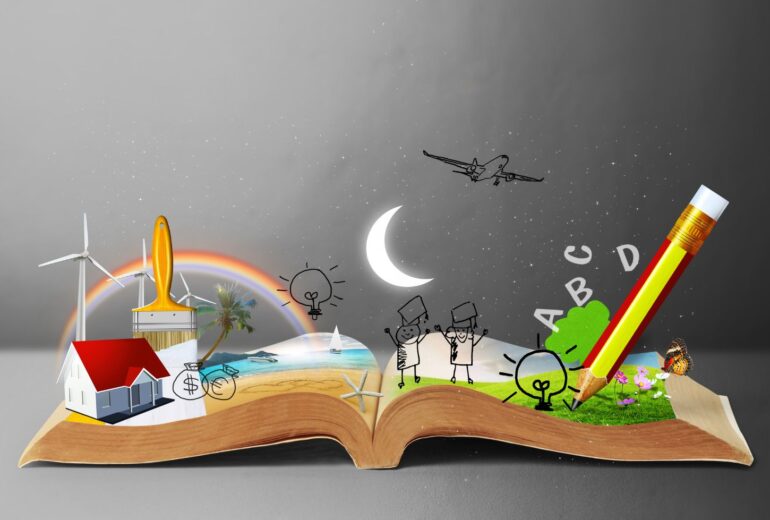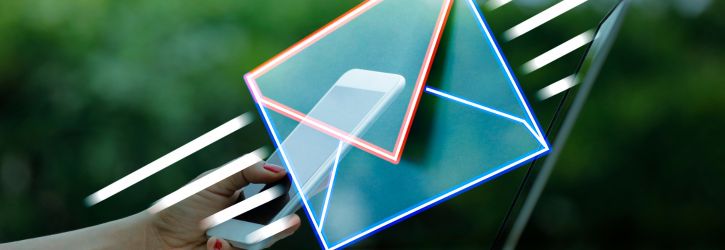1. 変わりゆく食卓と気候変動の関係
「最近、野菜や果物の旬がずれている気がする」「いつも食べていた魚が取れなくなった」――そんな変化を感じたことはないでしょうか? それは、気のせいではなく、気候変動の影響による「産地北上」や「水資源の偏在」が影響しています。
気温の上昇により、これまで南の地域で栽培されていた作物が北の地域でも生産できるようになり、逆に南では従来の作物が育ちにくくなっています。例えば、日本では米の生産地が東北や北海道にシフトしつつあり、かつての主力産地だった西日本では高温障害が増えています。
2. 産地北上とお米の変化:ランキングが示す新たな潮流
お米の銘柄ランキングにも、この「産地北上」の影響が現れています。日本穀物検定協会が発表する「米の食味ランキング」では、従来は新潟の「コシヒカリ」や秋田の「あきたこまち」などが上位を占めていました。しかし、近年は北海道産の「ゆめぴりか」や「ななつぼし」が高評価を受けるようになっています。これは、北海道の気温が上昇し、稲作に適した環境が広がった結果です。
一方で、西日本では高温障害が増え、かつての名産地でも品質が不安定になりつつあります。このように、気候変動が私たちの食卓に影響を与え、新しい食のトレンドを生み出しているのです。
参考:おいしいお米ランキング、最高品質が減少 九州で低下(日本経済新聞)
3. 水資源と産地北上:不可分の関係
作物が育つには適した気候だけでなく、水資源の確保も欠かせません。農業は世界の淡水使用量の約70%を占めると言われています。そのため、気温の変化と水資源の偏在は切り離せない問題なのです。
例えば、気温上昇によって乾燥が進む地域では水不足が深刻化し、稲作や野菜栽培が難しくなります。これが産地北上の背景にもなっています。逆に、降水量が増えたり、気温が適温になった地域では、新たな作物の生産が拡大しているのです。つまり、産地北上は単に気温の問題だけではなく、水資源の分布とも密接に関係しているのです。
4. 水資源を巡る新たな戦争
「水戦争」という言葉を聞いたことはありますか? これまでの戦争は土地や資源を巡るものが主でしたが、近年は「水」を巡る争いが顕在化しつつあります。
例えば、ナイル川流域ではエチオピアがダムを建設し、下流のエジプトとの対立が激化。また、インドとパキスタンは、インダス川の水資源を巡り長年緊張関係にあります。気候変動により降水パターンが変化し、一部の地域では水不足が深刻化しているため、こうした対立は今後さらに拡大する可能性があります。
水資源の豊富な日本においても水不足のリスクは無縁ではありません。農業用水の確保は今後の食料生産に直結する問題です。産地北上と水資源問題は切り離せず、食の安定供給には水資源の管理が不可欠なのです。
参考:ナイル川流域のエチオピアのダムとエジプトの対立(BBC)
参考:インダス川の水資源を巡るインドとパキスタンの緊張関係(The Diplomat)
5. 私たちにできること:企業・個人のアクション
企業の視点
- 地域資源を活用した循環型農業の推進(例:地元産の作物を使った食品開発)
- 水資源を守る技術の導入(例:節水型の農法や、水の再利用システム)
- 環境配慮型の事業戦略(例:脱プラスチックやエコパッケージの導入)
個人の視点
- 旬の食材を積極的に選ぶ(地域の気候に適した作物を支援)
- エシカル消費を意識する(フェアトレード商品やサステナブル認証の食品を選ぶ)
- 水の使い方を見直す(節水・雨水利用など)
6. Brightが考える未来のコミュニティビジネス
Brightでは、サステナビリティを軸にした地域ビジネスの可能性を模索しています。気候変動の影響をチャンスに変え、新たな農業や飲食ビジネス、観光の形を生み出すことで、持続可能な社会を創ることができます。例えば、地域の農産物を活用したコミュニティレストランの運営や、環境負荷の少ない観光プランの提供などが考えられます。
気候変動の影響は決して他人事ではなく、私たちの食卓やビジネスにも直結しています。今こそ、一人ひとりがアクションを起こし、持続可能な未来に向けた一歩を踏み出す時です。
名古屋大学大学院修了後、外資系電機メーカーでグローバル営業に従事し、アジア・アフリカでの日系企業の進出支援に従事。現在は合同会社エネスフィア代表および株式会社BrightのCSOとして、SDGsビジネスマスターや脱炭素アドバイザーなどの資格を活かし100社以上の中小企業支援に実績。さらに、BSIジャパン認定アソシエイト・コンサルタントおよびB Corp認証取得支援コンサルタントとしても活躍中。